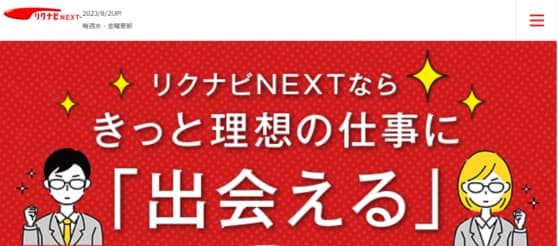※本記事は一部プロモーションを含みます
大学を中退するなら休学をしてギャップイヤーを経験しよう
最終更新日:2023年6月20日

当サイトを訪問している人の中には、大学を中退しようかどうか迷っている人もいると思います。
そのような人たちも、当サイトの内容を見て、大学中退者からでも就職活動を上手くやれば内定をもらえるのだと考えられたかもしれません。
しかし、現実問題として、新卒者などに比べて大学中退者は、大企業や有名企業への就職において不利になります。
また、学歴が昇進や給料などにも影響をおよぼす可能性があるので、できるならば卒業するのが賢明な判断です。
しかし、様々な理由があって大学中退を検討しているのだと思いますし、卒業することの価値を知っていても大学に通い続けることに抵抗を感じる人も多いと思います。
そういった方の場合は、ぜひ中退をする前に休学をしてほしいと思います。
休学をすることで、大学に通う意味を見つける人も多い
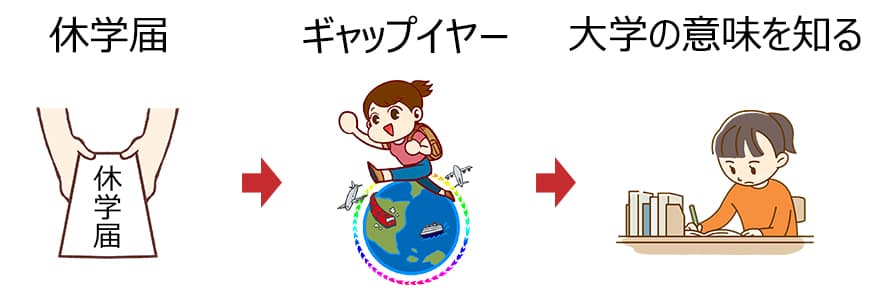
休学をするには、大学の事務所に休学の意思を伝え、休学の申請書を提出すれば数日から1ヶ月ほどで学長から許可がもらえ休学期間に入ることができます。
休学期間にも一定の大学費用がかかることが多いので、事務所でよく相談をしてから休学に入ることをおすすめします。
このようにして休学に入ってしまえば、最長で4年間は休学期間として自由に時間を過ごすことができます。
海外では、大学に入学する前に1年ほどのギャップイヤーという自由に過ごせる期間を設けて、その間にボランティアや長期の海外旅行、就業などを経験させる制度があります。
これらの経験から大学でどういったことを自分が学ぶべきかを知ることができ、目的意識を持って学業に励むことができるようになっています。
実際にギャップイヤーを導入している英国などにおいては、大学中退者が減少するというデータも出ています。
しかし、日本においてギャップイヤーを導入する大学はまだまだ少なく、今現在(2013年)において、やっと東大がギャップイヤーの導入に積極的になってきている程度です。
そういったことから、日本でギャップイヤーのようなことを経験しようと思うと、休学をするという選択肢が最も有力なものになってきます。
中退をする人の中には、大学でやることを見いだせなかったという人や、大学に払う費用がもったいないといった理由で中退する人は多いです。
こういったことを避けるためにも、一度休学をしてボランティアや就業経験を経ることで、大学に通えるということが貴重な時間であり、その中で学べることがたくさんあるのだと気づけるのではないかと思います。
休学をしても何もせずにダラダラしているなら意味はないですが、積極的に社会活動に参加することで大学に通う意味を再認識できる可能性があると思います。
大学を休学する場合には、
を参考にしてください。
履歴書に休学について書く際には、
を参考にしてください。
関連サイト
2024年最新版!大学中退者に人気の就職サイトBEST3
大学中退者が使っている就職サイト(就職エージェントと求人サイト)を、人気順に3位まで紹介します。
※ランキング調査期間:2023年10月15日~2024年1月15日
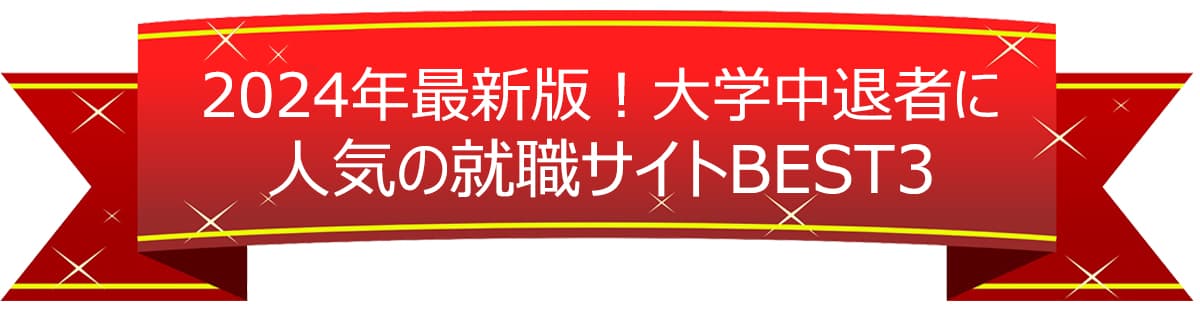
 ジェイック就職カレッジ |
ジェイック就職カレッジは、就職成功率81.1%(大学中退者に限ると90.7%)の実績を持つ就職エージェントです。 中退者向けの求人を紹介してくれたり、中退者向けの就職講座で、面接での中退理由の伝え方やマナーを学べます。 |
|---|---|
 リクナビNEXT |
リクナビNEXTは、大学中退者の利用者が多い人気求人サイトです。 様々な職種や地域の求人に加え、他では得られない大企業の求人も充実しています。 |
 第二新卒エージェントneo |
第二新卒エージェントneoは、20代に特化した就職・転職支援サービスです。 職務経験のない人だけで10,000人以上の就職支援実績があり、大学中退者にも人気があります。 |
大学中退者におすすめの就職サイトを全て見たい方は、以下からチェックしてみてください。
 大学中退者におすすめの就職サイト(就職エージェントと求人サイト)16選
大学中退者におすすめの就職サイト(就職エージェントと求人サイト)16選
当社カジュアル相談を活用してください
当社(株式会社ウェイズファクトリー)では、学校を中退した後の就職活動について無料で気軽に相談できる窓口を設けております。
当社のキャリアアドバイザーにメールか電話で相談できます。
- 「どの就職エージェントを利用すればよいかわからない」
- 「どのように就職活動を行えばよいかわからない」
- 「どのような職種が向いているのかわからない」
というような質問に就職支援15年以上の経験を元にお答えします。
また必要な方には、中退者が応募できる未経験歓迎の正社員求人を紹介することもできます。
ご相談したい方は以下の記事の下にあるフォームよりお申し込みください。
岸 憲太郎
・株式会社ウェイズファクトリー代表取締役
・関西大学総合情報学部卒業
人材紹介事業と就職や転職に関してのWEBメディア事業を行う(株)ウェイズファクトリーの代表をしています。
15年以上の就職支援経験を通じて、数百名の採用担当者や求職者と情報交換をしてきました。
それらの経験を社会に還元していくために、記事の監修だけでなく、編集にも深く関与して情報発信を行っています。
詳しいプロフィールは、こちらをチェックしてみてください。
プロフィール

 大学中退理由別の面接回答例文20選と大学中退理由ランキング
大学中退理由別の面接回答例文20選と大学中退理由ランキング 大学を休学するための手続き
大学を休学するための手続き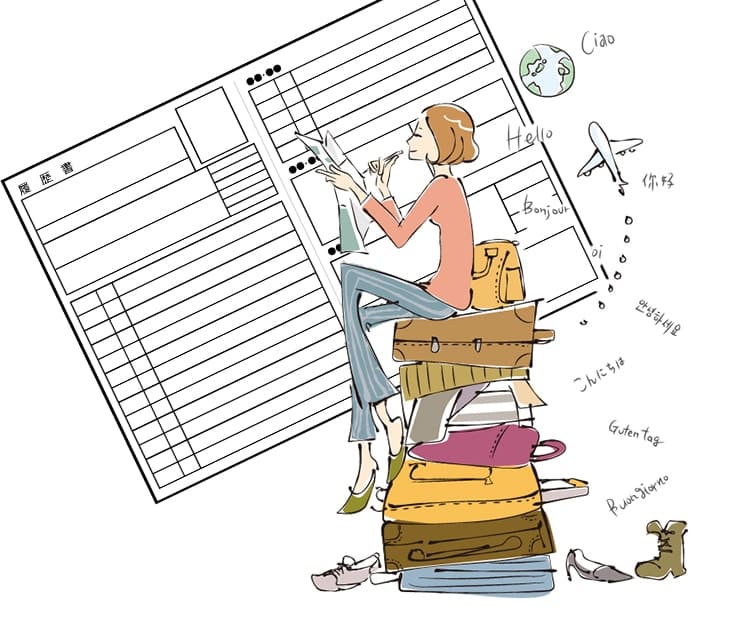 休学経験は、履歴書でどのように書くべき?
休学経験は、履歴書でどのように書くべき? 中退者向けカジュアル就職相談窓口
中退者向けカジュアル就職相談窓口




 子供が大学中退しそうになったら親ができること
子供が大学中退しそうになったら親ができること 大学中退が親不孝になる理由と対策。親との相談方法も紹介
大学中退が親不孝になる理由と対策。親との相談方法も紹介 大学中退をして留学する方法
大学中退をして留学する方法 大学中退後に時間があるなら英語の勉強もはじめてみよう
大学中退後に時間があるなら英語の勉強もはじめてみよう 天候不良に見舞われたときの就職活動方法
天候不良に見舞われたときの就職活動方法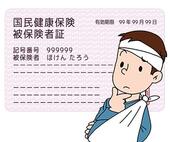 大学中退をした人も健康保険について知っておこう!
大学中退をした人も健康保険について知っておこう!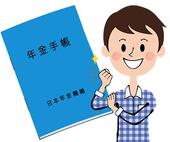 大学中退したら国民年金保険料を忘れずに支払おう!
大学中退したら国民年金保険料を忘れずに支払おう! 企業が求めている能力、社会人基礎力をチェックしてみよう
企業が求めている能力、社会人基礎力をチェックしてみよう 大学中退後には運動習慣を身につけよう
大学中退後には運動習慣を身につけよう 喫煙者を採用しない企業が増加中
喫煙者を採用しない企業が増加中 大学中退後に時間があるなら、ボランティアに参加しよう
大学中退後に時間があるなら、ボランティアに参加しよう 高校中退からの就職活動の現状
高校中退からの就職活動の現状 大学中退後、就職活動をする前にやっておきたいこと
大学中退後、就職活動をする前にやっておきたいこと 大学中退者がOB、OG訪問する方法
大学中退者がOB、OG訪問する方法 時事問題に強くなるように日頃から情報収集をしよう
時事問題に強くなるように日頃から情報収集をしよう 大学中退者も知っておこう!文系と理系の就職活動の違い
大学中退者も知っておこう!文系と理系の就職活動の違い 就職四季報を買って読んでみよう!
就職四季報を買って読んでみよう! 大学中退後の就職活動で必要な費用
大学中退後の就職活動で必要な費用 大学中退者が第二新卒になる前に知っておきたいこと
大学中退者が第二新卒になる前に知っておきたいこと 大企業と中小企業の違い
大企業と中小企業の違い 就職活動で習慣化の力を借りよう
就職活動で習慣化の力を借りよう 就職後に直ぐ辞めない方法
就職後に直ぐ辞めない方法 7年後をイメージして就職活動をはじめ夢を実現しよう
7年後をイメージして就職活動をはじめ夢を実現しよう 大学中退から内定後、就職するまでにする事
大学中退から内定後、就職するまでにする事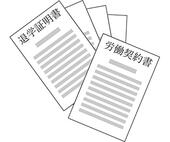 大学中退者が入社時に提出する書類一覧
大学中退者が入社時に提出する書類一覧 就職活動で使えるスマートフォンアプリ
就職活動で使えるスマートフォンアプリ 最近よく見かける就職活動指南塾は役だつの?
最近よく見かける就職活動指南塾は役だつの? 就職活動期間に風邪を引かないために
就職活動期間に風邪を引かないために 仕事をはじめてからも長く使えるWEBサービス
仕事をはじめてからも長く使えるWEBサービス 大学中退者のイメージを変えていこう!
大学中退者のイメージを変えていこう! 株価が上下して景気の先行きが見えないので、就職活動に躊躇します
株価が上下して景気の先行きが見えないので、就職活動に躊躇します こんな面接官は駄目駄目面接官
こんな面接官は駄目駄目面接官 大学中退者が入社前にチェックすべき労働条件
大学中退者が入社前にチェックすべき労働条件 大学中退をして後悔する人、後悔しない人の特徴
大学中退をして後悔する人、後悔しない人の特徴 退職理由を知って早期退職を防ごう!
退職理由を知って早期退職を防ごう! 未経験者は、行動に移しているだけでも評価が上がる
未経験者は、行動に移しているだけでも評価が上がる 大学の役割とは何か?
大学の役割とは何か? これからの社会人に期待される事
これからの社会人に期待される事 日本人の労働感はどんな感じ?働くのが好き?余暇を楽しみたい?
日本人の労働感はどんな感じ?働くのが好き?余暇を楽しみたい? 大学中退者の就職活動で、最大の問題はライバルがいないこと
大学中退者の就職活動で、最大の問題はライバルがいないこと 夏の暑い日に、少しでも快適に就職活動をする方法
夏の暑い日に、少しでも快適に就職活動をする方法 今、女性の営業職が求められている
今、女性の営業職が求められている 就職活動にパソコンは必要?スマホだけで十分?
就職活動にパソコンは必要?スマホだけで十分? 大学中退後に就職活動をする場合にも、大学図書館を活用しよう
大学中退後に就職活動をする場合にも、大学図書館を活用しよう 就職後の満足度を高めるために、就職前にできることとは?
就職後の満足度を高めるために、就職前にできることとは? ブラック企業は情報の開示レベルで見分けよう
ブラック企業は情報の開示レベルで見分けよう 大学中退者が就職する可能性が高い、中小企業の魅力とは?
大学中退者が就職する可能性が高い、中小企業の魅力とは?