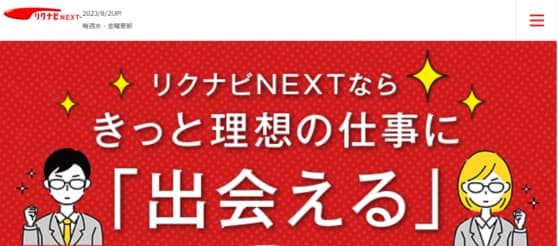※本記事は一部プロモーションを含みます
大学中退をして別の大学へ編入する方法
最終更新日:2023年9月26日

「違う分野の勉強がしたい」「やっぱり大学卒業の学歴が欲しい」という人は、別の大学に編入することでも実現できます。
ここでは別の大学に編入する方法を分かりやすく解説します。
大学中退後に選べる進路
大学中退後は別の大学に編入する以外に「就職する」「資格を取得する」「専門学校に入学する」など選べる進路があります。
以下の記事で大学中退後に選べる進路を紹介しているので、こちらも参考にしてください。
大学中退者に人気の就職エージェント
ジェイック就職カレッジ
| サービス内容 | 大学中退者向けの就職支援を行っており、大学中退者を採用したい企業の求人紹介や履歴書、面接対策をしてもらえます。 |
|---|---|
| 紹介求人 | 営業、広告・メディア、メーカー、商社、IT通信系、経理、事務等 |
| 対象地域 | 全国 |
| 特徴 | ・就職支援実績は23,000人以上 ・就職成功率は81.1%(大学中退者に限ると90.7%) ・入社後定着率は91.3% ・厚生労働省から有料職業事業者に認定 |
1. 編入とは

「編入」とは、習得した単位を活かして別の大学に途中学年から入ることを指しますが、大学を中退して他の大学に移る人だけが編入者ではありません。
- 短期大学
- 高等専門学校
- 専門学校
などを卒業後に大学に入学する場合も編入といいます。
大学や学部によって編入する時期はさまざまですが、3年次から始まる編入が一般的です。
編入には通常の編入試験以外に「推薦編入試験」と「社会人編入試験」があります。
推薦編入試験は以下の場合などに利用できます。
- 在籍している大学の学部長に、優秀者として認められ推薦書を書いてもらうことで別の大学に推薦編入をする
- 大学が同じ系列として短期大学も運営している場合に、短期大学から大学に推薦編入をする
推薦枠での編入であれば、通常の編入よりも優先的に編入が認められるので選考で有利になりやすいです。
ただし大学によって推薦編入ができない場合や推薦枠の数に違いがあるので、事前に確認をする必要があります。
社会人編入試験は、一度会社員とした勤務した経験があることを受験資格としており、年齢や社会人経験年数などを応募条件に含めている大学もあります。
社会人編入では他の編入枠よりも志望動機が重視される傾向があるので、大学編入が今後のキャリアにどう関係するのかなど、深い内容の志望動機を伝えることをおすすめします。
しかし現状では社会人編入を実施している大学は少ししかありません。
2. 別の大学に編入するメリット

大学を中退して別の大学に編入するメリットは4点あります。
- 進路変更できる
-
まず一番大きなメリットは「進路変更できること」です。
最初の大学生活を経験したことで本当に学びたいことが分かった人や、環境を変えたいと思っている人にとって、編入学はとても有効な選択肢といえます。 - 難関大学に挑戦できる
-
2つ目のメリットは国公立や有名私立大など「難関大学に挑戦できること」です。
大学編入試験は、英語や小論文、希望する学科の専門知識の3科目のみの大学もあるほど、試験科目が一般入試よりも少ないのが特徴です。
もちろん勉強は必要ですが、試験科目の多い一般入試では手の届かなかった大学に少ない科目で挑戦できます。 - 単位が無駄にならない
-
3つ目のメリットは「単位が無駄にならないこと」です。
編入先の大学では、これまで通っていた学校で習得した単位を認めてもらえるので、新しい大学では3年生もしくは2年生としてスタートできます。
計画的に編入すれば、編入前の学校と合わせて通算4年で卒業できるので卒業にかかる年数が他の大学生と変わりません。
しかし認定される単位数は各大学によって決められており、取得した単位が全て認められるわけではありません。
仮に90単位取得していたとしても認定される単位数は60単位程度の場合が多いです。 - 大卒の学歴を得られる
-
4つ目のメリットは「大卒の学歴を得られること」です。
大卒=仕事ができる訳ではありませんが、やはり大卒というだけで、同じ仕事でも給料が高くなったり正社員として採用されやすかったりする傾向があります。
大学中退をした人の中には、大学中退という学歴での正社員就職の難しさから「大学を卒業しておけばよかった...」と後悔している人が多いです。
大学中退をしてから何年経っていても編入可能な大学はいくつもあり、編入できれば約2~3年で大卒の学歴を得られます。
3. 編入の募集人数と倍率

3-1. 編入の募集人数は多くない
編入は本来欠員募集を目的としているため、その年の学生数によって編入制度の有無や募集人数が異なります。
残念ながらそもそも編入を行っていない大学・学部もあります。
募集人数は学部によっても異なり、学部の規模が大きいほど募集人数も多い傾向があります。
しかし規模の大きい学部でも5~20名程度の募集がほとんどで、小さな学部になると明確な募集人数は記載されず、「若干名」としている大学が多いです。
募集人数は、編入の時期が近くなると各大学のホームページに記載されるので何校かチェックしておきましょう。
3-2. 編入の倍率は有名大学になるほど高い
一般入試と違い編入では募集人数が「若干名」としか記載が無く、出願者数は毎年バラバラです。
そのため倍率も毎年異なり、
競争率の高い大学では8~10倍
という場合もあります。
特に国公立や有名私立大学など、大学の偏差値が高くなるほど倍率も高くなる傾向があります。
一般入試では手の届かなかった有名大学に、編入でチャレンジする現役大学生が多いからです。
有名大学以外でも編入はそもそも募集人数が少ないため、
倍率は2~5倍
と言われています。
こんなに倍率が高いことを聞くと「編入受験を諦めようかな...」と思うかもしれませんが、編入試験出願者の中には記念受験の人も多く受験者全員が本気で編入対策をしているわけではありません。
また一般入試ではセンター試験の結果から志望校を決める人がほとんどで、受験者の学力は大抵同じくらいです。
しかし編入試験ではセンター試験のような志望校を決める基準が無く、出願条件を満たした人なら誰でも受験できるので、受験者の中には志望大学に学力が伴っていない人もいます。
以上のことから開示されている倍率より実際のライバルは少ないので、募集人数の少なさや倍率の高さを見て編入を諦めたり、志望校を下げるのは勿体ないです。
編入学受験は受験日が被らなければ何校でも受けられるので、合格率を上げるためにも試験内容の似ている大学を何校か受験することをおすすめします。
4. 編入には出願資格が決められている

4-1. 編入に必要な在学期間と単位数
編入学の出願資格には前大学の「在学期間」があります。
必要な在学期間は大学によって異なるものの編入学の場合は、
「大学2年次修了者」
と定めている場合が多いです。
また休学していた期間を除いて2年以上在学していることを出願資格としている大学や、2年生までの在学期間に修得した単位数の規定がある大学もあります。
規定の単位数は、
- 60単位
- 62単位
のどちらかのケースが多いですが、30単位程度でも2年次から編入できる大学や、休学期間とは関係なく「2年次を終了」して規定の単位数を修得していれば出願可能な大学もあります。
また大学中退者(大学中退予定者)が編入試験を受験する場合は、大学中退又は大学在籍の事実や成績を証明する必要があります。
そのために以下のような証明書が必要になります。
- 「退学証明書」
- 「在籍証明書」
- 「成績証明書」
以下の記事で証明書の発行方法について解説しているので、参考にしてみてください。
 大学中退者は就職時に退学証明書が必要?中退を証明する書類4種類と発行方法
大学中退者は就職時に退学証明書が必要?中退を証明する書類4種類と発行方法
また「まだ1年生だけど他の4年制大学に入り直したい」という人には「転入学(転学)」制度があります。
転入学は、学校間で手続きを行い1日も開けずに学校を移る制度で、1年以下だけしか在学していない人も利用できます。
「転入学(転学)」も大学や学部によって出願資格や入試内容が異なるので、事前に確認が必要です。
4-2. 編入には英語の資格が必要なことがある
編入の出願をするときに、TOEFLやTOEICのスコアカードや実用英語技能検定(英検)の合格証明書など、英語能力を証明する書類の提出を求める大学や学部があります。
外国語学部など語学を学ぶ学部であれば、基準点以上でないと出願できないこともありますが、ほとんどの場合は何点であっても出願できます。
しかし点数はもちろん合否に関係するので、高得点を取得していた方が合格率は上がります。
英語の資格とは別に編入試験では英語問題が多く出題される傾向があるので、どちらにしても英語の勉強が必要なことが多いです。
5. 編入試験はどんな問題が出題されるのか?

5-1. 編入試験は受験科目が少ない
編入試験は一般の入試より受験科目数が少なく、試験内容も大きく異なります。
編入の試験科目は大学や学部によって異なりますが、多くの大学が3、4科目程度と少なく試験科目は以下からよく出題されています。
- 英語
- 志望学部の専門科目
- 小論文
- 志望動機
- 面接
試験科目は少ないですがどの科目も求められるレベルが高いと言われています。
志望学部の専門科目については学部生と同等程度の知識は必要なことが多いので、これまで学んできたことと全く違う学部に挑戦する場合はしっかり勉強をする必要があります。
- 外国語が関係する学部の場合には、対象言語の能力試験を受けたり、資格試験の証明書を提出する必要があります。
- それ以外の文系学部では、一般的な筆記試験よりも学部に関係した論文を提出させることが多いです。
- 理系学部では、授業についていけるように基礎的な知識を問う試験や、論文試験が課されることが多いです。
また面接では就職活動の面接と同じように、自己PRをしたり志望動機を伝える必要があります。
面接では第一印象が重要なのでマナーにも気をつけましょう。
このように編入試験は試験内容が一般入試とは異なりますが、試験内容や対策法など編入試験に関する情報が少なく、情報収集に苦戦したという声が多いのが現状です。
最初にできる情報収集法として、試験内容を大学に貰いに行ったり郵送してもらえるか問い合わせる方法があります。
それでも情報が少なく対策が難しい人は、編入対策をしてくれる予備校に通うのも一つの手です。
予備校は費用がかかりますが、編入の過去問をもらえたり小論文の指導をしてもらえるなど効率よく編入試験対策を行えます。
5-2. 編入試験では志望動機が重視される
編入を出願する際には「志望理由書」の提出が必要だったり、面接で志望動機を詳しく聞かれたり、どの大学でも志望動機が重視されます。
志望理由書は
- 「どのような理由で編入するのか」
- 「なぜその大学に編入しようと思ったのか」
を記入して提出します。
この書類は入学選考に利用されるので、
- 編入理由について相手の納得がいく説明をする
- 志望動機を熱意を持って伝える
- 入学後の学業への意気込みなどを伝える
必要があります。
志望理由の内容は「大卒という学歴が欲しいから」「以前の大学では勉強についていけなかったから」という理由では説得力が弱いです。
「この大学・学部での勉強を活かして、今後キャリアをこんな風に広げていきたい」
「○○の経験からどうしてもこの学部に入って専門分野の勉強がしたい」
など前向きに勉強に励みたい気持ちをエピソードを交えて具体的に伝えましょう。
大学は学業に励んでくれる生徒を入学させたいと考えているので、入学後に学びたいことを具体的に伝えられれば高評価を得られます。
6. 大学編入は就職活動に影響するのか?

6-1. 自分を成長させるための大学編入はアピールポイントになる
大学編入を考えたとき「大学編入をすると後の就職活動に悪い影響が出るのではないか」と不安に思う人は多いです。
しかし大学編入という学歴によって採用されにくくなることはほとんどありません。
確かに大学編入の経験がある人は少ないので、採用担当者からどういった理由で編入したのか質問されることは多いです。
大切なのは大学編入について質問されたときに、採用担当者が納得できる前向きな理由を伝えることです。
〈大学編入理由の例〉
塾のアルバイトがきっかけで将来は教育の仕事がしたいと思うようになり、教育の授業が充実している今の大学に編入しました。
家庭の事情で経済的に苦しくなり、編入前の私立大学の学費を支払うことが厳しかったので、国公立大学へ編入しました。きっかけは経済的理由でしたが、編入前より高いレベルの大学編入試験は、自分を成長させることができました。
経済の分野で有名な〇〇教授のいる研究室で学びたかったので、編入しました。
採用担当者の多くは編入について詳しくないので「自分を成長させるための編入だった」「編入の勉強で自分を成長させることができた」ということを伝えて前向きな印象を持ってもらいましょう。
前向きな編入理由はマイナスポイントにならず、むしろ勉強に対する意識の高さはアピールポイントにもなるので、編入の勉強の大変さを自己PRとして話すこともできます。
もし編入前の大学より編入後の大学の方が偏差値が低い場合は「学びたい分野が変わったから」といった理由であれば採用担当者も納得しやすいです。
6-2. 大学中退から編入までブランクがある場合は伝え方に注意する
大学を中退してから別の大学に編入するまでの期間が2年以上空いている場合、履歴書上では何をしていたか分からない空白期間となり、あまり良い印象を与えることができません。
- 「どうして編入まで期間が空いてしまったのか>」
- 「どうして一度大学を中退したのか」
など採用担当者にはさまざまな疑問が浮かびます。
このような採用担当者の疑問を解消し、納得させられる理由を伝えることがポイントです。
以下の例を参考にしてみてください。
経済的な理由で大学を中退し就職しましたが、大学を卒業できなかったことをずっと後悔していました。中退後に営業職として勤務したことで、経済学を学びたいという思いが強くなり、経済学部のある大学に編入しました。
このように明確に学びたいことがあったと伝えることで「ただ大卒の学歴が欲しかったのかな」と思われずに済み、自分のキャリアを考えた上で行動できる人という印象を与えられます。
また中退理由は経済的事情などやむを得ない事情である方が面接官を納得させやすいです。
「編入前の大学の授業のレベルが低かったから」など編入前の大学を悪く言うことはやめておきましょう。
6-3. 大学編入をすると就職活動が忙しくなる
大学編入の学歴が就職活動に悪い影響を及ぼすことはほとんどありませんが、大学編入をすると就職活動のスケジュールがハードになることがあります。
編入した直後は、履修登録やゼミ活動の開始など慣れない環境でしなければならないことが多いです。
大学編入の多くが3年次からスタートなので、編入先の大学に慣れてきた頃に就職活動が始まり忙しくなるということになりがちです。
また人によっては認められる単位数が少なく、編入していない通常の大学生より単位取得自体がハードになることもあります。
7. 通信制大学と放送大学について

7-1. 通信制大学・放送大学のメリット
通信制大学と放送大学の一番のメリットは「いつ・どこで」勉強しても大学を卒業できることです。
中退後に社会人として就職している人でも、交通の便が良くない地方に住んでいる人でも、マイペースに勉強できます。
ただし定期的に大学に行って担当教授の指導を受けたりする「スクーリング」に出席する必要があります。
しかし最近はインターネット授業を導入することで、以前よりも通学日数が短くなっている学校も増えてきています。
また通学と通信制の2つの過程がある大学の多くは、通信制の学費の方が安くなっています。
同じ大学なのに通学する場合の1年分程度の学費で卒業できる大学もあります。
同じ仕事でも大卒の学歴があるだけで給与が高かったり、昇格するスピードが早くなったりする企業も多いので、働きながら単位取得をしている人も多いです。
7-2. 通信制大学・放送大学への編入方法
- 通信制大学への編入方法
-
現在40以上の大学が通信教育を行っており、大学院と短期大学を合わせて約24万人が学んでいます。
通信制大学では3年次編入だけでなく、前大学に1年以上在学していた人を受け入れる2年次編入学を実施している大学が多いのが特徴です。
編入学のための出願資格は、- 2年次編入...1年以上在学し、かつ30単位以上の修得
- 3年次編入...2年以上在学し、かつ60単位以上の修得
多くの通信制大学では原則として書類選考が行われており、いわゆる学科試験はありません。 - 放送大学への編入方法
-
2019年現在、全国でおよそ9万人が放送大学に在籍しています。
大学中退者は「2年次」または「3年次」に編入学することが可能です。
放送大学では入学のための選抜試験はなく、年2回の出願期間に入学手続きを行います。
また通信制大学でも放送大学でも、他大学で修得した単位が、編入学した大学での単位として認定される制度があります。
認定可能な単位の内容や単位数は大学によって異なりますが、単位修得証明書や単位修得見込証明書などの提出が必要になります。
通信制大学や放送大学については、以下の記事で詳しく解説しているので、チェックしてみてください。
 大学を仕方なく中退したなら、通信大学や放送大学も考えよう
大学を仕方なく中退したなら、通信大学や放送大学も考えよう
8. 専門学校に編入するという選択肢

8-1. 大学の単位を、専門学校で認定してもらえる制度がある
専門学校は「即戦力となるための、実践的な知識と技術を学ぶ」ことが目的です。
そのため実習科目が多く、また企業と提携して最先端の技術を学んでいる専門学校もあります。
そんな専門学校へ編入する際、大学で修得した単位を専門学校で活かすことができる制度があります。
どの単位が認められるのかなど、詳細は専門学校ごとに規定されているので事前に確認することをおすすめします。
ただし専門学校は、2年次から編入学をするようなことは基本的にできないので1年から勉強を行う必要があります。
8-2. 専門学校から大学への編入学もできる
専門学校で実践的な知識と技術を習得しても、もっと研究を深めたいと思うかもしれません。
修学年数2年以上の専門学校を卒業して専門士になると、4年制大学に編入学できます。
また修学年数4年以上の専門学校を卒業して高度専門士になると大学院に進学できます。
専門学校への入学について興味がある方は、以下の記事を参考にしてみてください。
9. 編入しても引き続き奨学金は使える?

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を利用している4年制大学の現役学生が、他の4年制大学に編入学した場合、多くのケースでは引き続き利用できます。
ただし両方の大学に申し出る必要がありますので、手続きについては両方の大学に事前に確認してください。
大学中退から編入学まで期間が空いている場合は、JASSOの判断次第です。
以前の大学でJASSOの奨学金を貸与されていた場合は、返済状況や残額などを参考にするといわれています。
編入学した大学で学ぶために新しく奨学金の貸与を希望する人は「奨学金は入学後に振り込まれる」ということを忘れないでください。
つまり入学金を含む入学のための諸経費は、事前に用意しなければならないのです。
各大学や地方自治体でも独自の奨学金制度を設けていますので、そうした制度の利用も検討しながら大学生活に必要な学費計画を立てるとよいでしょう。
参考:「転学・編入学」独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
10. 退学届けを提出するタイミング

あなたが4年制大学の2年次として在学しながら、他大学への編入学を希望していたと仮定します。
「編入学するためには、今の大学を中退しなければ」と出願前に退学届を出してはいけません。
退学届を提出するのは、他大学の編入試験に合格したことが分かってからで大丈夫です。
合格が分かる前に退学届を提出しなければ、他大学の編入試験に失敗した場合も、そのまま同じ大学に残れるので、突然学生ではなくなるリスクがありません。
また出願資格の多くが「2年次修了」や「2年以上在学」とされていたり、 修得単位数(特に外国語)の規定があるので、編入を考えている人は退学届は慎重に扱うようにしましょう。
大学を退学するための手続き方法については、以下の記事で解説しているので、手続きを行う際に参考にしてください。
 大学を退学(中退)する手続き。退学届の見本ともらい方・書き方も紹介
大学を退学(中退)する手続き。退学届の見本ともらい方・書き方も紹介
11. まとめ
ここまで他大学への編入について解説しました。
大学によって編入の出願条件や試験内容が違っているなど、不明確なことが多い編入制度。
募集人数も少なく諦めそうになるかもしれませんが、試験科目が少なかったり、これまでの単位を活かせたりするなどメリットも多くチャレンジする価値のある制度です。
編入制度は各大学によって異なるので、志望大学が絞れたら大学の事務局に問い合わせてみてください。
2024年最新版!大学中退者に人気の就職サイトBEST3
大学中退者が使っている就職サイト(就職エージェントと求人サイト)を、人気順に3位まで紹介します。
※ランキング調査期間:2023年10月15日~2024年1月15日
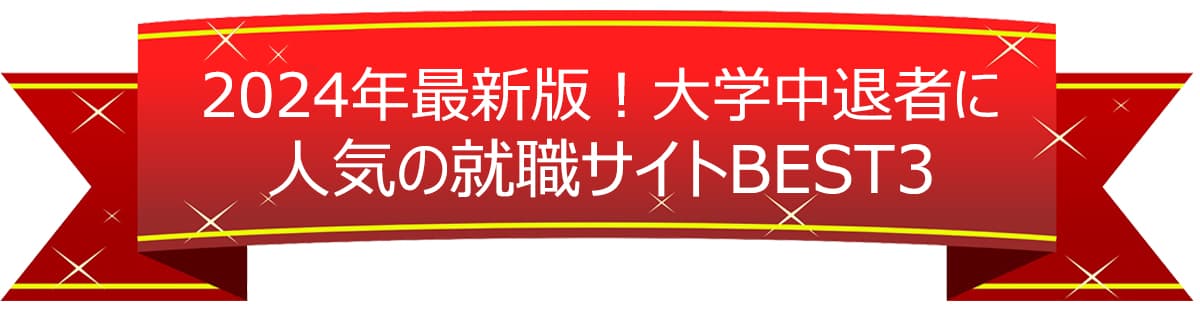
 ジェイック就職カレッジ |
ジェイック就職カレッジは、就職成功率81.1%(大学中退者に限ると90.7%)の実績を持つ就職エージェントです。 中退者向けの求人を紹介してくれたり、中退者向けの就職講座で、面接での中退理由の伝え方やマナーを学べます。 |
|---|---|
 リクナビNEXT |
リクナビNEXTは、大学中退者の利用者が多い人気求人サイトです。 様々な職種や地域の求人に加え、他では得られない大企業の求人も充実しています。 |
 第二新卒エージェントneo |
第二新卒エージェントneoは、20代に特化した就職・転職支援サービスです。 職務経験のない人だけで10,000人以上の就職支援実績があり、大学中退者にも人気があります。 |
大学中退者におすすめの就職サイトを全て見たい方は、以下からチェックしてみてください。
 大学中退者におすすめの就職サイト(就職エージェントと求人サイト)16選
大学中退者におすすめの就職サイト(就職エージェントと求人サイト)16選
当社カジュアル相談を活用してください
当社(株式会社ウェイズファクトリー)では、学校を中退した後の就職活動について無料で気軽に相談できる窓口を設けております。
当社のキャリアアドバイザーにメールか電話で相談できます。
- 「どの就職エージェントを利用すればよいかわからない」
- 「どのように就職活動を行えばよいかわからない」
- 「どのような職種が向いているのかわからない」
というような質問に就職支援15年以上の経験を元にお答えします。
また必要な方には、中退者が応募できる未経験歓迎の正社員求人を紹介することもできます。
ご相談したい方は以下の記事の下にあるフォームよりお申し込みください。
岸 憲太郎
・株式会社ウェイズファクトリー代表取締役
・関西大学総合情報学部卒業
人材紹介事業と就職や転職に関してのWEBメディア事業を行う(株)ウェイズファクトリーの代表をしています。
15年以上の就職支援経験を通じて、数百名の採用担当者や求職者と情報交換をしてきました。
それらの経験を社会に還元していくために、記事の監修だけでなく、編集にも深く関与して情報発信を行っています。
詳しいプロフィールは、こちらをチェックしてみてください。
プロフィール

 大学中退のメリット・デメリットとその後の進路12選を解説
大学中退のメリット・デメリットとその後の進路12選を解説
 大学中退後は、専門学校への入学も考えてみよう!
大学中退後は、専門学校への入学も考えてみよう! 中退者向けカジュアル就職相談窓口
中退者向けカジュアル就職相談窓口




 大学退学と除籍の違いと、除籍された人の就職方法
大学退学と除籍の違いと、除籍された人の就職方法 大学中退者は就職時に退学証明書が必要?中退を証明する書類4種類と発行方法
大学中退者は就職時に退学証明書が必要?中退を証明する書類4種類と発行方法 大学中退後に授業料は返ってくるの?
大学中退後に授業料は返ってくるの? 中退した大学に再入学するための手続き
中退した大学に再入学するための手続き 大学を休学するための手続き
大学を休学するための手続き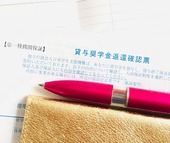 大学中退後の、奨学金の手続き
大学中退後の、奨学金の手続き 仮面浪人後に大学中退して別の大学に入学する方法
仮面浪人後に大学中退して別の大学に入学する方法